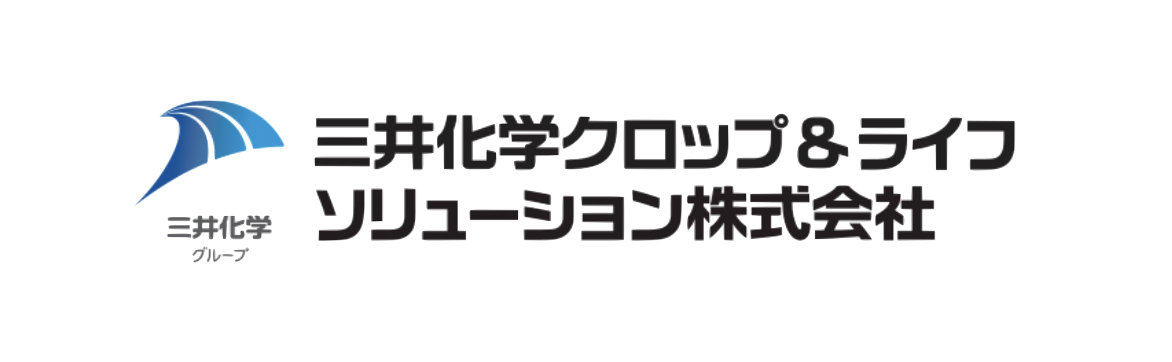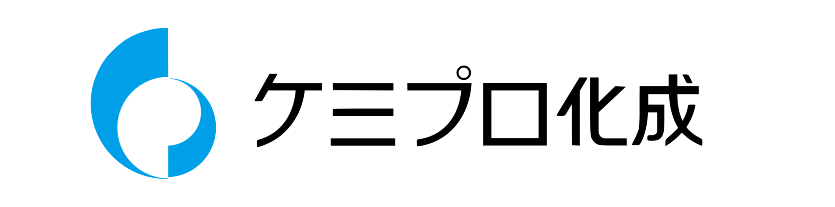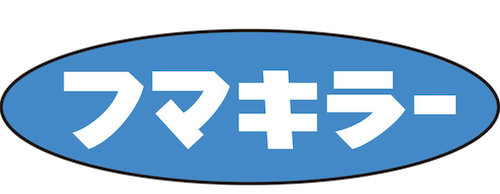新着情報
目的
本会は,人間の生活環境を清潔,快適ならしめるため,昆虫および動物の学術的・総合研究の発展ならびに被害防止技術の向上を促進することを目的とし,もって公共の福祉に寄与することとする.
会長挨拶
2025年2月から一般社団法人日本環境動物昆虫学会の会長に選出されました板倉修司です。平井規央副会長と引土知幸副会長とともに、会員や理事、編集委員会、企画委員会、年次大会実行委員会、賞選考委員会、生物保護と環境アセスメント部会などの皆様のご支援のもと、本会の発展のために尽力したいと思います。
本会は2020年11月に一般社団法人となり4期目を迎えます。法人の目的は定款に定められていて、定款第4条には「この法人は、人間の生活環境を清潔、快適ならしめるために、昆虫および動物の学術的・総合研究の発展ならびに被害防止技術の向上を促進することを目的とし、もって公共の福祉に寄与することとする」と目的が記載されています。
また、定款第5条には「この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う」と記され、
(1)研究発表会、シンポジウム、セミナー、懇談会、見学会、市民公開講座などの開催、
(2)機関誌「日本環境動物昆虫学会誌」(「環動昆」)の発行およびその他の出版物の刊行、
(3)調査研究、
(4)防除に関する技術の研究開発、
(5)研究部会の設置、
(6)内外の学会、研究機関、公共団体などとの連携協力、
(7)研究の奨励および研究業績等の顕彰、
(8)その他前条の目的を達成するために必要な事業、
以上8事業が挙げられています。
このように本会の目的は、学問分野と個々の研究の発展に加え、昆虫と動物による被害防止技術の向上まで広範にわたっています。基礎研究から応用研究まで多様な研究者が集い、年次大会や講演会などでの交流と情報交換、機関誌「環動昆」での研究成果の公表、さらには会員企業様による製品開発を通して、研究成果を広く社会に還元するところが本会の特徴であります。大学や公的研究機関の研究者と企業に所属する研究者が情報交換を行うことのできる機会、若手研究者が研究成果を発表し会員との意見交換を通して研究をさらに発展させ研究力を向上させる機会、一般の方が昆虫や動物に関する最新の研究成果に触れる機会などを、これまでと同様に提供できるよう、本会の活動を継続して行きたいと思います。
昨年の年次大会の際に、平林前会長から年次大会時の子育て支援を検討するように申し受けました。保育士を常駐させた託児室の設置が望ましいところですが、まずはおむつ替えやお子様が自由に遊べる部屋を年次大会時に確保するところから始めたいと思います。 編集委員会のご尽力により、機関誌「環動昆」の投稿システムのオンライン化への準備が着々と進められています。
これまでは、電子メールで原稿を本会事務局に送付した後に編集委員会へ再配信するシステムでしたが、オンライン化により編集委員長が原稿の投稿と同時に投稿原稿を取扱うことが可能になります。論文審査の迅速化につながり、研究成果の公表までの時間が短縮されるため、研究者にとっては非常に有益であると考えられます。
近年、人工知能(AI)ツールの使用が進んできています。一概に研究へのAIの利用を禁止することは得策ではありませんが、論文投稿や研究発表の際は、データの収集や分析、図表の作成や修正などに、どのAIツールをどのように使用したかを明示する必要があります。ただし、投稿原稿の作成へのAIツールの使用は、その使用が必要不可欠とは考えられませんので、一般的に認められないと考えられます。AIツールの使用については、今後の理事会や総会で検討して行く必要があります。投稿規定に関しては、編集委員会で検討していただいています。 会員の皆様が研究成果を発表し意見交換しやすい学会運営に努めて行きたいと考えております。
会員の皆様には引き続きご支援、ご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
2025年3月
一般社団法人 日本環境動物昆虫学会会長
板倉 修司
沿革
創立:1988年11月
機関誌第1巻第1号発行:1989年7月
第1回企画委員会主催講演会:1990年6月
日本学術会議第6部(農業総合科学)加盟、広報協力学術団体に指定:1991年5月
第1回環境アセスメント動物調査手法に関する講演会:1991年6月
第1回研究奨励賞授与:1994年11月